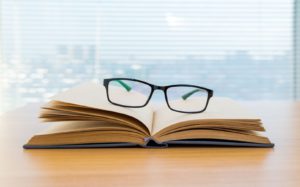第443回 < ESG投資の過去、現在、未来 >

コロナ禍前後に多くの投資家が投資テーマとして、「ESG投資」を挙げていました。環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)を重視した投資を指し、会社、経済、社会の持続可能性を念頭に置いてできたコンセプトです。これまでのESG投資にはいくつかの節目があったと思います。1997年に気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)が京都で開催され、日本人にもなじみの深い「京都議定書」が採択されました。先進国は、温室効果ガスの排出量を1990年比で5%減少させることを目標とし、このときは、ESG投資という言葉は一般的ではありませんでしたが、様々な国々で地球温暖化問題解決に向けての取組が開始されました。
その後、2006年に国連がPRI(責任投資宣言、Principles for Responsible Investment)を制定し、国連が投資機関に対してESGの概念を組入れた投資を行うように推奨し、機関投資家、運用者等に対してPRIへの署名を求めるようになりました。この際、PRIがESG投資を再定義し、また、企業が社会や環境に与える影響を配慮すべきであり、その考え方を遵守させるためには、投資家、株主からの要請が不可欠だとの考え方のもと、機関投資家にPRIへの署名を働き掛けました。
日本においてもその頃からESGに配慮する投資信託が誕生しましたが、残高が大きく伸びたのは、日本の機関投資家がPRIに署名する動きを加速した2015年以降だったかと思われます。特に、最大の機関投資家である、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が2015年にPRI署名を行い、2017年からはESG指数に連動する株式投資に取り組み始めたことがキッカケになったのではないかと思います。更に、2020年以降、コロナ禍を経て人々のESGへの意識が高まったことから、世界的なESG、SDGsの意識が高まった結果、ブームはピークを迎えます。
その後、ESG投資に対しては、実際には環境に配慮していない会社が、うわべだけを取り繕い顧客や投資家を獲得する「グリーンウォッシング」の懸念が大きくなるなどの批判がでたり、エネルギー業界を中心に米国で反ESGの動きが活発化したりしたことなどで、ESG投資に対する逆風が見られました。更に、第2期トランプ政権発足に伴い、米国が地球温暖化対策に関するパリ協定からの離脱を表明し、また、多様性・公平性・包摂性(DEI)を重視する流れにも背を向けるなど、2006年以降のESG投資拡大の流れにブレーキがかかっています。
トランプ政権下の米国の動きに影響され、今後も当面の間、これまでのESG投資の考え方に対する批判や、従来型のESG投資をテーマにした投資信託の残高減少は続くものと思われます。しかし、温暖化問題は日ごとに大きく人々の生活に影響を与え、従来型の企業統治の問題点が明らかになり、不寛容な社会の構造による社会損失が表面化し続けている昨今、これらの課題を解決しなければいけないという人々の意識の方向性が大きく変わることもないと思われます。
事実、大きく拡大を続けるプライベートエクイティ投資やベンチャー投資の現場において、ESGに配慮した投資を行うことは、大手機関投資家の観点から、当たり前の要請になっており、この傾向が変わることはないと思われます。一方、署名機関投資家が遵守すべき、現在のPRIの6つの原則は極めて汎用的な内容となっていますが、その中で求められているESG課題自体は変化する可能性があります。また、国連が制定したSDGsの17項目の目標と169のターゲットすべてに取組める企業はありませんし、その内容自体も変化し得ると思います。ESGやSDGsに関して、異なる国、業界、時代をまたいだ画一的な正解は存在せず、我々当事者が周囲と協力し、その時々に実効性の高い基準を考え、遵守し、更にそれらをアップグレードし続ける必要があると考えています。 このような変遷を踏まえて、当社の投資運用事業におけるESGの取組についても社内で考え続けていく必要性を感じています。