第449回 < 金融システムレポート2025年10月号について >
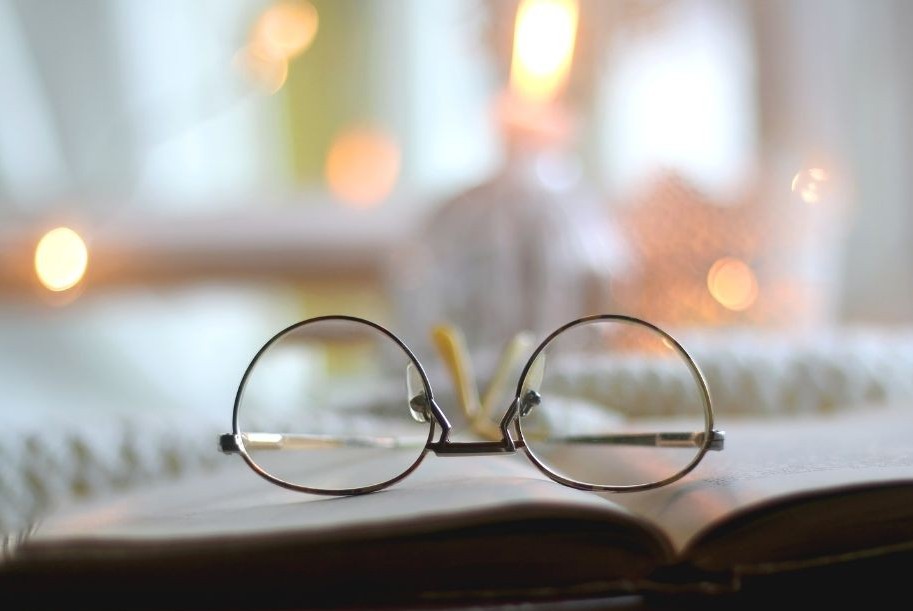
日本銀行の金融システムレポート2025年10月号が公表されたので、内容について考察したいと思います。本コラムでは、2017年から継続的に金融システムレポートの内容を追い続けていますが、前回の2025年4月号では、日本の金融機関とプライベート・エクイティファンドの関係について、これまでになく掘り下げた内容となっていました。そして、今回の10月号では、「ノンバンク部門を巡るリスクと金融安定上の含意」と題して、ヘッジファンドの動向を大きく取り上げています。これは、近年、米国のヘッジファンドによる日本向けの投資額が急増していることと、ヘッジファンド自体のレバレッジが一段と高まっているとみられることから、国内の金融資産価格、特に国債価格のボラティリティが急速に上昇するリスクを懸念してのことと考えられます。
それでは、あらためて今回のレポートの内容を見ていきます。はじめに、レポートでは、「わが国の⾦融機関は、内外の⾦融市場や実体経済に影響を与えるリーマンショック型のストレスや、地政学的リスクの顕在化に伴って、世界貿易量が⼤きく減少し、グローバルに物価や⾦利が上昇する複合的なストレス等に耐え得る、充実した資本基盤と安定的な資⾦調達基盤を有している」と論じています。また、アメリカ発の通商政策の影響がある中、国内企業の収益、債務返済能力は良好であると分析しています。一方、近年大きく上昇した株価、不動産価格については、「イールドスプレッド」の縮小の観点から、価格調整の可能性を警戒した論調が見られます。
世界経済の減速懸念、海外大手ハイテク企業株式の調整リスク、米国におけるインフレの再加速等も警戒される中、米欧におけるクレジット市場や商業不動産の先行き懸念や、中国経済の動向の不確実性なども指摘されています。しかし、国内金融機関においては、金利上昇による収益性の改善と有価証券投資に対する慎重姿勢が観測されていることを理由に、レポート全体を通じて金融機関の財務リスクに対する警戒感はあまり感じられないように思います。国内金融機関の主要な有価証券投資である国債価格が足下の金利上昇に伴い評価損を増していますが、こちらに関しては金利上昇に伴う利ザヤの拡大に伴う業務純益の改善と、時間の経過に伴うロールダウン効果による債券価格の上昇があることから、大きな懸念点とはなっていませんでした。
したがって、本レポート上において指摘されている懸念は、「グローバルな債券市場におけるヘッジファンドのプレゼンス拡大」と、それに伴う債券価格のボラティリティ上昇リスクにあるように思われます。米国で活動する大規模なヘッジファンドによる日本国債の裁定取引の拡大と取引回転率の上昇は、欧米金融機関が仲介者となり、日本の金融機関から日本国債を大量に調達していることを示唆しています。これらの日本国債は現物取引及び、裁定取引の担保にも用いられており、グローバルな金融資産価格の変動が、日本国債の価格変動により大きな影響を与える可能性が考えられます。今回、投資銀行等へのヒアリングを通じて、レバレッジの規模をリサーチしていますが、海外のヘッジファンドが主体であるため全体像を把握しにくいことも、警戒感を高めている理由かもしれません。
今回の金融システムレポートを通じてもいくつかの学びがありました。引き続き、金融市場の動向を様々な観点から注視していきたいと思います。


