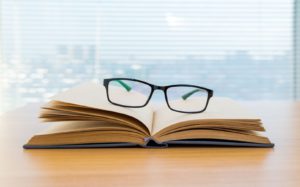第445回 < 米国による関税措置をあらためて「囚人のジレンマ」から考える >

本コラムでは、2018年の第一次トランプ政権時の米中関税問題が発生した際、ゲーム理論の中核をなす、「囚人のジレンマ」の観点から最終的な着地点を想像しました(第304回 <ゲーム理論からみる米中貿易交渉> – あいざわアセットマネジメント株式会社役職員ブログ)。
第二次トランプ政権における関税措置は前回の中国のみを対象としたものとは異なり、日本を含めて数多くの貿易国の相互関税を引き上げる措置となっています。今年初めに不法移民や違法薬物の流入を理由に国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づいて、カナダ、メキシコ、中国に追加関税を発令したことから始まり、4月には全世界からの輸入に対して10%のベースライン関税を課したのみならず、日本を含む貿易赤字額の大きい国に対して個別に相互関税を課しました。
中国が2018年の時と同様に、また、カナダ、EU等が報復措置を取りましたが、多くの国々は米国からの再報復を恐れて水面下での交渉を続けている状況です。高い相互関税は、各国において免除期間も終了し、2025年半ばから実行されます。米国企業の多くは関税上昇によるコスト増をすでに顧客価格に転嫁しているとのことで、物価上昇を助長する要因となっています。日本においても、消費者物価指数の上昇が継続しており、2025年6月20日公表の5月の物価は前年同月比3.5%の上昇となり、昨年12月以降、6ヶ月連続して3%台後半の物価上昇となっています。日本企業も米国の関税措置の影響で純粋な輸入価格の上昇に対応し、また、予防的な値上げを行っていることを考えると、物価上昇トレンドは比較的高い水準で定着していることが伺えます。
あらためて、今回の関税措置をゲーム理論の枠組みで考えてみたいと思います。米国は世界一の大国の立場から貿易制限を課すことで利益を享受できることが前提になります。「最適関税理論」に則れば、大国が関税を課して輸入を制限すれば輸入需要の減少によって輸入財の国際価格が下落し、最終的に大国は利益を享受できます。これは輸入量の少ない小国には当てはまらず、大国にのみ有効な理論です。この前提で、大国対小国の間での関税率を選ぶ関税設定のゲームを「囚人のジレンマ」の構造の中で考えると、大国と小国の間でもお互いに対して高い関税を課す状況が「ナッシュ均衡」となります。将来的に複数の国(プレーヤー)から報復的な課税(制裁)が生じる場合、大国にとっても脅威になりますが、大国が自国の圧倒的有利を自認する、あるいは近視眼的な立場に立つ限り、自由貿易はナッシュ均衡にならず、貿易制限をかけ続けるという選択肢が正解となりえます。
したがって、米国を圧倒的世界一の立場とし、自らの強さを誇示するというトランプ大統領の立場から考えると、今回の関税措置は合理的な判断と考えられます。今後、米国以外の各国が協調し、多くの取引相手が報復的措置を取るような事態が容易に想定されることにならないか、長期的視野を持ち自由貿易を推進する政権が誕生しない限り、今回の関税措置が継続することになります。
輸出入の多い日本企業では今回の関税措置が業績に大きな影響を与えることになります。各企業の業績予想に、どの程度今回の関税措置に関する情報が織り込まれているのか注視していく必要があると思われます。